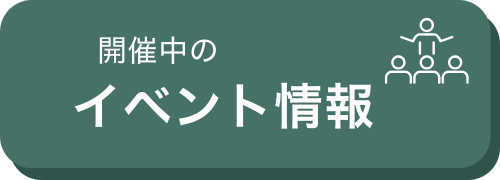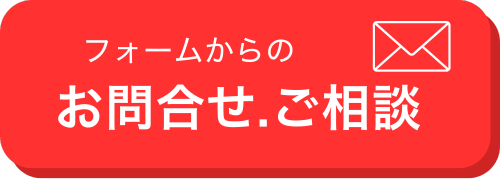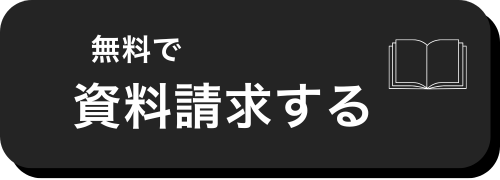「注文住宅を建てるなら、ダブル断熱にしたほうがいいかな?」と悩んでいませんか?新築するなら「冬は暖かく、夏は涼しい家」にしたいですよね。そんなときに気になるのがダブル断熱です。
一方で「コストが高いのでは?」とか「メンテナンスが大変?」といった不安もあります。実際、何も知らずに採用すると、予想以上の初期費用やランニングコストに悩まされることも……。
本稿では、ダブル断熱のメリットだけでなく、気になるデメリットや対策を詳しく解説します。納得して断熱工法を選択できるようにわかりやすくお伝えしますので、最後までご覧ください。
ダブル断熱のデメリットとは
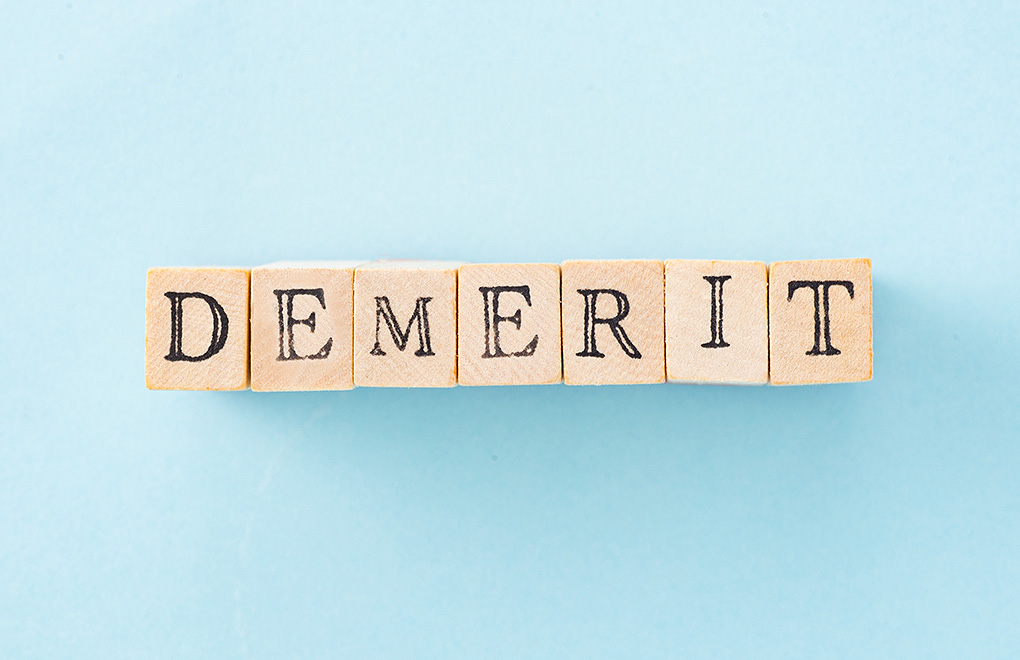
ダブル断熱は、内断熱(充填断熱)と外断熱(外張断熱)の両方を組み合わせる断熱工法です。外部からの熱の影響を受けにくくなり、室内の温度環境の快適度がアップします。
- 充填断熱:外壁や屋根などの構造体の中に断熱材を詰める工法
- 外張断熱:外壁や屋根の外側に断熱材を張って構造体をくるむ工法
従来は内断熱が主流で、一部の建築会社が外断熱を採用していました。なぜなら、外断熱は断熱性を向上できる反面、施工に手間がかかりコストアップしやすいからです。
しかし近年では、電気代の高騰や新築住宅が達成すべき省エネ基準の厳格化により、高断熱住宅への関心が高まっています。この流れの中で、ダブル断熱工法にも注目が集まりました。
ここからは、ダブル断熱工法の特徴をメリットとデメリットの観点から解説します。まずは、デメリットを3つご紹介しましょう。
- 建築コストが高くなる
- 施工できる業者が限られる
- メンテナンスの負担が増える可能性がある
順番に詳しく解説しましょう。
建築コストが高くなる
ダブル断熱は内外二重に断熱材を施工するため、材料費と手間がシングル断熱より増加し、建築コストが高くなりがちです。
建築コスト増に対して冷暖房費削減でどの程度回収できるか、検討する必要があるでしょう。お住まいの地域の気候によっては、高断熱化による光熱費メリットが小さい場合もあります。
また、投資回収に時間がかかる点を踏まえて導入を判断することが重要です。補助金制度を活用したり、長期間住むことで光熱費削減の恩恵を最大化したりする工夫が必要でしょう。
施工できる業者が限られる
ダブル断熱は、断熱に関する幅広い知識と高い技術力が求められる工法で、施工できる業者が限られます。とくに外張断熱は、現状では施工実績の豊富な建築会社がまだまだ少ない状況です。
ダブル断熱は壁厚が増すため、狭小地ではプランニングが難しくなるなど、設計上の制約も生じます。施工会社選びに苦労する可能性があるでしょう。
ダブル断熱を経験の浅い業者に任せてしまうと、不具合を招くリスクがあります。たとえば、施工ミスによって壁の内部で結露が発生してしまい、建物の耐久性を損なう恐れがあります。
一方、施工なれしたミスの少ない業者なら、耐久性を損なわずにダブル断熱を実現してくれます。材料のロスが減るため、ムダなコストも抑えられるでしょう。
ダブル断熱を採用する場合は、経験豊富な会社を選び、施工方法や使う断熱材の仕様を事前に確認することが大切です。
各社で材料や工法に差があるため、構造見学会などに訪れ、信頼できる施工品質か見極めてから契約すると安心です。施工中も、施工品質をしっかりチェックしましょう。
メンテナンスの負担が増える可能性がある
ダブル断熱は、将来的に断熱材の更新をおこなう際、改修コストがシングル断熱に比べて増える可能性が高いでしょう。
ダブル断熱は、断熱材を更新する際、外断熱と内断熱の二重の費用がかかります。外断熱を貼り替える際は、一般的に足場の設置や外壁の撤去の費用も必要になります。
ですから、ダブル断熱を採用する場合は、将来のメンテナンス費用も考慮して選びたいところです。また、更新頻度を減らすため、耐久性の高い断熱材を選ぶことも大切です。
ダブル断熱で得られる効果・メリット

つづいて、ダブル断熱で得られる効果やメリットを4つご紹介しましょう。
- 断熱性の向上(省エネ効果の向上)
- 快適性の向上(室内温度の安定・ヒートショック対策)
- 耐久性の向上(建物の劣化抑制・資産価値の維持)
- 防音性の向上(外部騒音の低減)
順番に、詳しく解説していきます。
断熱性の向上(省エネ効果の向上)
ダブル断熱を採用すると、住宅の断熱性能が向上し、冷暖房のエネルギー消費を抑えられます。
ここで、断熱材で断熱性能を高める際の基本ルールをおさらいしておきましょう。
| 熱伝導率 | 断熱材の性能は熱伝導率(W/m・K)の低さで決まる。熱伝導率の低い材料を使うと、熱が移動しにくくなる。 |
|---|---|
| 材料厚 | 厚みが増すほど、熱の伝わりにくさ(熱抵抗値)が向上する。ただし、施工性やコストとのバランスも重要。 |
| 熱橋 | 熱橋とは、柱や梁などの熱が通りやすい部分のこと。熱橋と外気が直に接触する部分を減らすのがポイント。 |
| 気密性 | 隙間があると、高性能な断熱材を使っても断熱効果が損なわれる。断熱材や気密テープの適切な施工が大切。 |
内断熱に加えて外側にも断熱材を施すダブル断熱では、上述の基本ルールを達成しやすくなります。その結果、外気温の影響を受けにくくなり、冷暖房効率が向上します。
冷暖房効率が向上したダブル断熱住宅は、省エネ効果が高まるため、光熱費を大幅に削減できます。しっかり光熱費を削減したい方には、ダブル断熱がおすすめです。
快適性の向上(室内温度の安定・ヒートショック対策)
ダブル断熱は、家全体をまるで魔法瓶のように包み込めるため、快適性が以下のようにアップします。
- 家内の温度ムラが小さくなる
- 年間を通して快適で健康的な生活環境を確保できる
- 夏は涼しく冬は暖かい環境を低い光熱費で維持しやすくなる
部屋の温度が低いと、血圧が上昇したり睡眠の質が悪くなったりすることがわかっています。また、寒い家で過ごすと、冬場のヒートショックリスクが増加します。
ヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、心臓や血管に負担をかける現象のことです。ヒートショックを起こすと、心筋梗塞や脳梗塞などにつながる恐れがあります。
一方、暖かい部屋で過ごすと、上述のリスクを抑制できるだけでなく、脳年齢を高く維持できる可能性があります。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
WHO(世界保健機関)は、冬の室内温度を18度以上に保つことを強く推奨しています。健康と室内環境に気を配りたい方には、ダブル断熱がおすすめです。
耐久性の向上(建物の劣化抑制・資産価値の維持)
ダブル断熱にすると、建物の耐久性が向上し、資産価値を維持しやすくなります。
ダブル断熱は、外側の断熱材で構造体をくるむため、温度変化による構造体への負担が減ります。構造体への負担が減れば、建物の長寿命化が期待できるでしょう。
ちゃんと施工すれば、壁の内部の結露も防げますので、木材の腐朽や断熱材の劣化も予防できます。そのような腐朽や劣化の予防は、さらなる長寿命化につながります。
ただし、適切なメンテナンスを怠ると、どんな家でも劣化の進行を早めてしまいます。長期的な視点でメンテナンス計画を立て、耐久性と資産価値を維持しましょう。
防音性の向上(外部騒音の低減)
ダブル断熱の家は、厚みのある断熱層が壁の防音性能を高めるため、外部からの騒音の侵入を低減する効果があります。
また、気密性を上げると隙間が減り外部からの音が侵入しにくくなるため、防音性を高めます。静かで快適な住環境を実現したい方には、高気密高断熱住宅がおすすめです。
ただし、防音性能は屋根や外壁だけで向上できるものではありません。異厚複層ガラス窓など、防音性能の高い窓を採用することも忘れないようにしましょう。
注文住宅でダブル断熱を採用するときの注意点

最後に、注文住宅でダブル断熱を採用するときの注意点をふたつご紹介します。
- 窓や換気設備の断熱性能にも気を配る
- 防湿と気密性、換気計画にも気を配る
どちらも、ダブル断熱の効果を生かすための大切な要素です。それぞれ、詳しく解説しましょう。
窓や換気設備の断熱性能にも気を配る
「ダブル断熱にするから、これで断熱はバッチリ」と考えるのは少し気が早いです。床・壁・屋根の断熱だけでなく、窓や換気設備などの断熱にも気を配りましょう。
「屋根、外壁、床、窓」など、建物の内外を隔てる境界を「外皮」と言います。じつは、外皮の中でもっとも熱の流出入が多いのは「窓」です。
換気設備からも、外壁と同程度の熱の流出入がありますので、住宅全体で断熱バランスを最適化することが大切です。
参考:日本建材・住宅設備産業協会「開口部からの熱の出入りは、どの位あるのですか?」
とりわけ窓の断熱を怠ると、省エネ効果が半減してしまいます。高断熱窓を採用し、ダブル断熱を生かしましょう。
防湿と気密性、換気計画にも気を配る
高断熱化すると気密性が高まるため、計画換気が不可欠になります。計画換気を適切におこなわないと、健康を害したり内部結露(壁の内部で生じる結露)を生じたりするリスクが高まるでしょう。
計画換気とは、居室全体の空気が2時間で入れ替わるように換気をコントロールすることを指します。快適で健康的な住環境を維持するための重要な仕組みです。
高断熱住宅では、隙間を極力なくしつつ24時間換気で湿気を排出することで、結露やカビを防ぎます。気密性の低い住宅は、空気がよどんでしまうため、計画換気ができません。
万が一、断熱層内で結露が発生すると、見えない箇所でカビの繁殖や腐食を進行させる恐れがあります。カビや腐食は、断熱性能の低下や構造体の劣化、健康被害の原因になりかねません。
対策として、計画換気や高い気密性、そして防湿シートの適切な施工が不可欠です。家の断熱性能を高める際は「防湿、気密性、換気計画」にも気を配りましょう。
まとめ:ダブル断熱はメリットとデメリットを考慮して採用しよう
ダブル断熱には、断熱性・快適性・耐久性・防音性の向上など多くのメリットがあります。一方で、施工コストやメンテナンスの課題もあるため、総合的な視点で採用を検討することが大切です。
また、屋根や外壁などのダブル断熱だけでは「完璧」とは言えず、窓や換気設備の断熱にも気を配る必要があります。防湿や気密性、計画換気も重要ですので、実績豊富な建築会社にご依頼ください。
三原防水ドット工務では、ダブル断熱住宅のご相談を承っております。「ダブル断熱のことを詳しく知りたい」「新築のプラン図面が欲しい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。