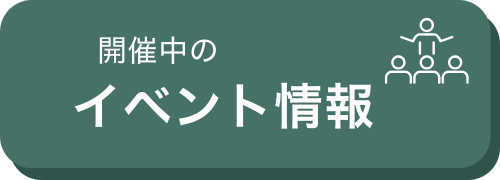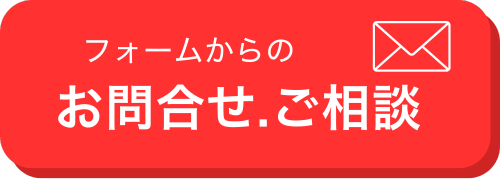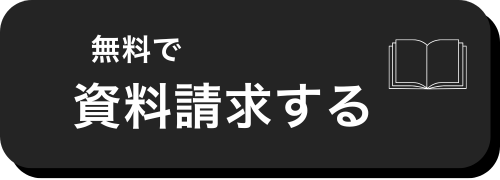家づくりで、建築会社から「ネオマフォーム」をすすめられ、気になっている方が少なくないのではないでしょうか。高性能で人気の断熱材ですが、実は注意すべき欠点もあります。
「価格の高さ、紫外線・衝撃への弱さ、シロアリ被害のリスク」など、デメリットを知らずに採用すると後悔につながることも。高い買い物だからこそ、失敗したくないですね。
本稿では、ネオマフォームの欠点と魅力を分かりやすく解説するとともに、他の断熱材との比較もご紹介します。納得感を持って断熱材を選ぶためのヒントが満載です。
》埼玉県でネオマフォーム断熱の家を新築するなら「家はシェルッソ」へ
旭化成の断熱材「ネオマフォーム」の欠点とは?
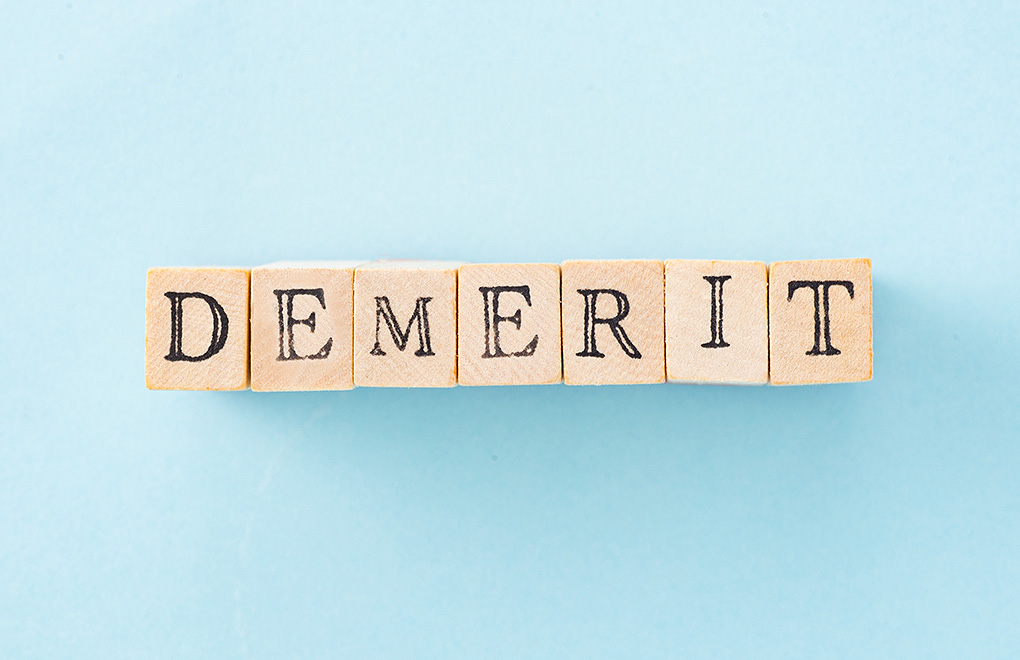
省エネ住宅を検討している方がよく耳にするのが、「ネオマフォーム」という断熱材です。旭化成が開発した高性能断熱材で、住宅の省エネ性能を高めるために多くの建築会社が採用しています。
ただし、すべての断熱材には必ず弱点があり、ネオマフォームも例外ではありません。メリットとデメリットの両面を理解してから採用することが、住み始めてからの「満足」につながります。
ではさっそく、ネオマフォームの主なデメリットを3つご紹介しましょう。
- 他の断熱材に比べて価格が高め
- 人工樹脂であるため紫外線や物理的衝撃に弱い
- シロアリの食害に遭う恐れがある
他の断熱材と比較すると、ネオマフォームは極めて優れた断熱性能を持っています。しかし、価格が高く、コストパフォーマンスで考えた場合は必ずしも優位とは言えません。
さらに、紫外線や物理的衝撃、シロアリの食害に対して注意が必要です。それぞれ、もう少し詳しく解説していきます。
他の断熱材に比べて価格が高め
ネオマフォームの最大のデメリットは「価格の高さ」でしょう。
▼なぜ価格が高いのか
ネオマフォームは、断熱材の中でも高性能な部類に入ります。しかし、他の断熱材に比べて原材料費と製造コストが高いため、製品価格も高額です。
たとえば、一般的によく使われる「グラスウール」と比較すると、ネオマフォームの価格はおおよそ2~4倍になります。
建築費全体から見れば断熱材は一部の費用に過ぎませんが、それでも総額に影響を与えることは否めません。とくに延床面積の広い家では、その価格差が顕著に表れます。
▼長期的に見ればコストメリットも
この「価格の高さ」は一見すると大きなハードルに感じられますが、視点を変えれば違った見方もできます。
たとえば、外張り断熱。薄くても高い断熱性能を発揮できるネオマフォームなら、外壁や屋根の厚みを抑えつつ必要な断熱性を確保できます。
また、省エネ性能が高まることで光熱費の削減につながったり、健康的に暮らせることで医療費を削減できたりと、長期的に見ればコストメリットを得られる可能性があります。
人工樹脂であるため紫外線や物理的衝撃に弱い
ネオマフォームは人工樹脂(プラスチック)を主原料とする断熱材です。そのため、紫外線や物理的な衝撃には比較的弱いという特徴があります。
採用にあたっては、この点を理解しておくことが大切です。
▼紫外線に弱い
ネオマフォームをはじめとするプラスチック系断熱材は、直射日光にさらされると劣化が早まる傾向があります。変色したり、強度が落ちたりする原因となるため、施工時には注意が必要です。
具体的には、外壁材や防水シートでできるだけ早く覆い、紫外線を直接浴びないようにすることが大切です。
現場で保管する際も、屋内で保管するか、ブルーシートなどでしっかり養生して紫外線を避ける工夫が求められます。
放置すると性能低下につながりますが、きちんと管理すれば問題ありません。
▼物理的衝撃に弱い
ネオマフォームは高い断熱性能を誇る一方で、ボード自体の強度はそれほど高くありません。とくに角や端に力が加わると、割れたり欠けたりする恐れがあります。
ですから、運搬や施工時の取り扱いには細心の注意が必要です。グラスウールのように柔軟性のある素材と比べると、より丁寧に扱わなければならない点はデメリットと言えるでしょう。
採用する際は、ネオマフォームの施工実績が豊富な建築会社を選ぶと安心につながります。特性に合わせた適切な施工管理をおこなってもらいましょう。
シロアリの食害に遭う恐れがある
ネオマフォームを含む発泡プラスチック系の断熱材には、シロアリによる食害のリスクがあります。
シロアリは、断熱材そのものを好んで食べるわけではありません。しかし、移動のためにトンネル(蟻道)を掘ったり、そのかすを餌にしたりするケースがあります。
とくに、床下等の湿気がこもる場所はシロアリ被害が起きやすいため注意が必要です。防蟻処理が施された製品を選ぶ、あるいは施工時に防蟻対策をしっかり実施することが欠かせません。
一方、無機質素材であるグラスウールやロックウールは、シロアリに食害されにくいとされています。
そもそも「ネオマフォーム」とは?

ネオマフォームは、旭化成が製造・販売している高性能フェノールフォーム断熱材です。
数ある断熱材の中でも優れた断熱性能を持ち、近年では省エネ住宅やZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)にも幅広く採用されています。
ここでは、ネオマフォームのベースとなっている「フェノールフォーム」について、基本的な特徴を確認してみましょう。
フェノールフォームとは
フェノールフォームとは、フェノール樹脂に発泡剤や硬化剤を混ぜて膨らませ、板状に成形した発泡プラスチック系断熱材の一種です。
住宅の断熱材として長年使われてきた、信頼ある素材です。
▼最大の特長は、断熱材の中でもトップクラスの断熱性能
フェノールフォームの最大の特長は、断熱材の中でもトップクラスの断熱性能を持つことです。壁や屋根などに用いることで、少ないエネルギーで快適な室温を維持しやすくなります。
たとえば、猛暑日の昼下がりに「エアコンが効かない」と感じることがないでしょうか?高断熱の住宅なら、外気の熱が侵入しにくいため、エアコンが効きやすくなります。
▼断熱性能が高いため、必要な厚みが少なくて済む
フェノールフォームは、他の断熱材に比べて、必要な断熱性能を得るための厚みを薄くできます。つまり、外壁や屋根を厚くしすぎることなく、省エネ性の高い家を実現できるのです。
このような特長は、とくに「外張り断熱」で効果を発揮します。外張り断熱では、断熱材の厚みがそのまま建物の体積の増加につながり、建築コストや施工手間を増やす要因となります。
断熱材の厚みを少なくできれば、屋根や外壁、窓枠などの面積を抑えられます。狭小地のような限られた敷地では「設計の自由度が高まる」というメリットもあります。
フェノールフォームの魅力
フェノールフォームは、断熱材に求められる基本性能を高いレベルで備えています。中でも「熱伝導率、耐久性、安全性」の3点に優れており、安心して長く使える素材です。
▼熱伝導率が極めて低い
繰り返しになりますが、フェノールフォームは熱伝導率が極めて低く、断熱性が非常に高い素材です。
熱伝導率とは、熱の伝わりやすさを示す指標で、値が小さいほど「熱を伝えにくい」ことを意味します。主な断熱材の熱伝導率を比較してみましょう。
| 繊維系 |
・グラスウール:約0.05~0.03 ・ロックウール:約0.05~0.03 ・セルローズファイバー:約0.04~0.035 ・インシュレーションボード:約0.05~0.035 |
|---|---|
| 発泡樹脂系 |
・ポリスチレンフォーム (押出法):約0.04~0.022以下 ・ポリスチレンフォーム (ビーズ法):約0.045~0.03 ・硬質ウレタンフォーム (ボード):約0.035~0.022以下 ・硬質ウレタンフォーム (吹き付け):約0.04~0.023 ・フェノールフォーム:約0.04~0.022以下 |
ご覧のとおり、フェノールフォームは熱伝導率が断熱材の中でもトップクラスに低く、効率よく省エネ性を高めることができます。
▼経年劣化が少ない
フェノールフォームは劣化しにくい断熱材です。熱で発泡・硬化したフェノール樹脂は化学的に安定しており、変質や分解が起きにくくなります。
また、内部にある独立気泡構造の膜が丈夫なため、気泡内の断熱ガスが漏れにくく、長期間「断熱性能」を維持できます。
さらに、水をほとんど吸収しないため、水分による劣化リスクも抑えられます。一方、グラスウールなどの繊維系断熱材は、湿気を吸収すると断熱性能が著しく低下します。
▼安全性(難燃性・耐水性)に優れている
ネオマフォームの主原料であるフェノール樹脂は「熱硬化性樹脂」と呼ばれ、熱に非常に強い性質を持っています。
たとえば、炎に直接さらされても溶けたり燃え広がったりせず、表面が炭化して延焼を遅らせる働きをします。火源がなくなると自然に燃焼が止まる「自己消火性」も持ち合わせています。
さらに、燃焼時に発生する煙や有毒ガスが少ない点も安心材料と言えます。そのため、避難時の安全性を高める断熱材として評価されています。
》フェノールフォーム断熱材とは?特徴とメリット・デメリットを解説
断熱材は何がいい?メリット・デメリットを比較

マイホームを建てる際、断熱材選びは快適な暮らしと光熱費に直結する重要なポイントです。
しかし「どの断熱材が自分の家に合っているの?」「たくさん種類があって何を選べばいいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
断熱材のメリット・デメリット比較表
ここでは、主要な断熱材のメリット・デメリットを一覧表で比較してみたいと思います。
ご自身のライフスタイルやご予算、建てる場所の環境に合わせて最適な断熱材を選ぶための参考にしてください。
| 断熱材 | 断熱性 | 耐久性 | 難燃性 | 防水性 | 防音性 | 防蟻性 | 施工性 | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラスウール | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | ◎ |
| ロックウール | △ | 〇 | ◎ | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
| セルローズファイバー | △ | 〇 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | × | △ |
| インシュレーションボード | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ |
| ポリスチレンフォーム (押出法) | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | 〇 | 〇 |
| ポリスチレンフォーム (ビーズ法) | 〇 | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | 〇 | ◎ |
| 硬質ウレタンフォーム | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 硬質ウレタンフォーム (吹付) | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | × |
| フェノールフォーム | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | △ | △ | 〇 | × |
ご覧のとおり断熱材にはそれぞれ個性があり、「これさえ選べば正解」という万能なものはありません。重視するポイントによって最適解が変わります。
また、どの断熱材も施工の質によって性能に差が出るため、信頼できる施工会社に依頼することも忘れてはいけません。
断熱材選びのポイント
断熱材は住宅の快適性や省エネ性能に直結するため、さまざまな項目をチェックして総合的に判断することが大切です。
中でも重要なのが、「断熱性能・コストパフォーマンス・施工性」です。
▼求める断熱性能
まず大切なのは「どの程度の断熱性を求めるか」という点です。断熱性能は「熱伝導率」という数値で表され、値が小さいほど性能が高いことを意味します。
ただし、熱伝導率だけで断熱性能が決まるわけではありません。断熱材の厚みも、断熱性能に影響します。つまり、「どの断熱材をどれくらいの厚さで使うのか」が重要です。
ネオマフォームなどのフェノールフォームは、薄い厚みでも高い断熱性能を実現できるため、外張り断熱など壁厚を抑えたいケースに向いています。
▼コストパフォーマンス
断熱材選びでは、単価の安さだけでなく「必要な性能を得るのに、どれだけ費用がかかるか」で考えることが重要です。
たとえば、グラスウールは熱伝導率が低くありません。しかし、低コストを生かして厚みを増せば、しっかり断熱性を確保できます。コストパフォーマンスの高い断熱材と言えるでしょう。
加えて、施工の手間や施工箇所の制約、そして空間を広く使えるといった付加価値も考慮に入れることが大切です。
▼施工性
施工する場所や工法によって、適した断熱材は異なります。
たとえば、壁や屋根では隙間なく施工することが重要です。吹付タイプの硬質ウレタンフォームなら、複雑な形状の部分でも充填しやすく、密着性もよいため長期的に効果を維持できます。
一方で袋入りのグラスウールは、湿気が多い、あるいは施工精度が低いとずり落ちて「断熱欠損」を生じる恐れがあります。コスパだけで選ばず、施工者の技術とセットで考える必要があります。
まとめ:欠点を理解すれば、ネオマフォームは有力な選択肢
ネオマフォームには「価格の高さ、紫外線・衝撃への弱さ、シロアリリスク」といった注意点があります。欠点を知らずに採用すると、住み始めてから後悔することになりかねません。
一方、ネオマフォームは「薄くても高性能、劣化が少ない、火や水にも強い」といった魅力も兼ね備えています。欠点を理解したうえで生かせるなら、間違いなく有力な選択肢となるでしょう。
断熱材に完璧な製品は存在せず、必ず長所と短所があります。だからこそ特徴をしっかり理解し、ご予算や自宅の条件に合ったものを選ぶことが、納得のいく家づくりにつながります。