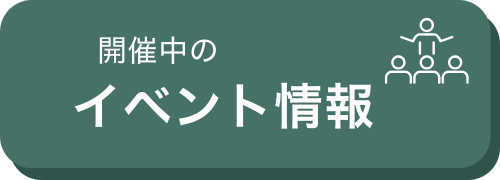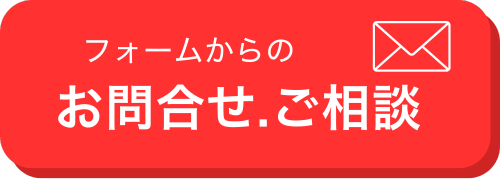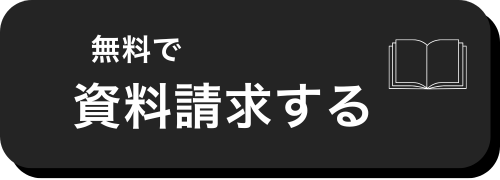「外断熱にすると後悔するって本当?」⸺ 注文住宅を検討する人の多くが、一度は不安に思うポイントです。実際に住んでから「失敗した」と思いたくないですよね。
たしかに外断熱には初期費用の高さや施工リスクなど、注意すべき点があります。しかし一方で、断熱性能や快適性、建物の寿命を延ばすといった大きなメリットもあるのです。
本稿では、外断熱が「危ない」と言われる理由や、失敗しないための対策をわかりやすく解説します。長所と短所を比較すれば、後悔のない選択ができますよ。
外断熱にすると後悔する?知っておきたいデメリットと対策
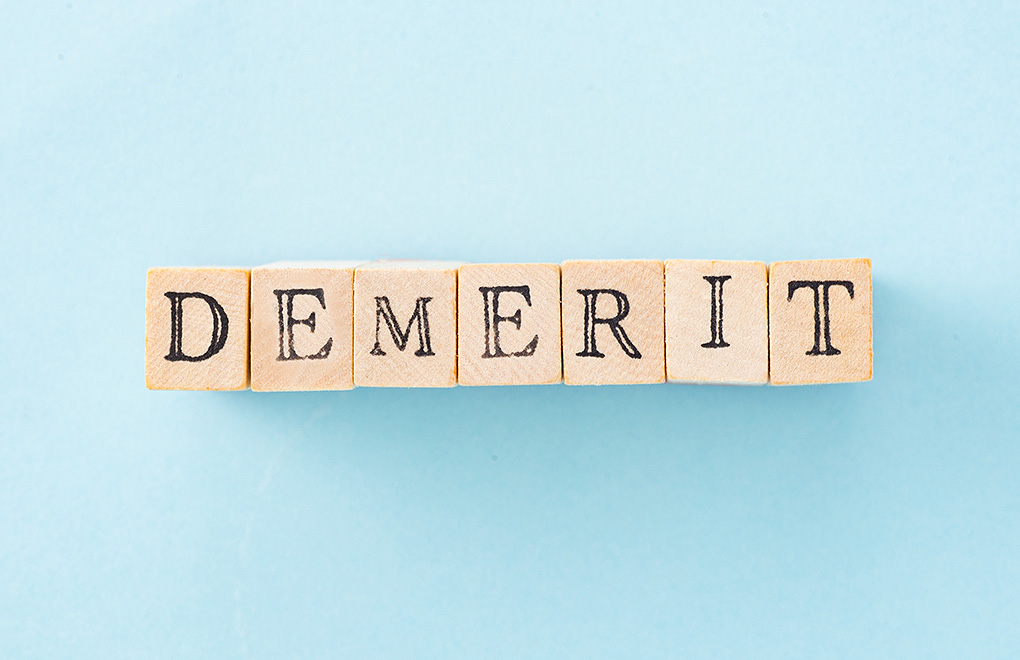
外断熱(外張り断熱)は、快適で長持ちする家づくりに役立ちます。
しかし、一方で注意しなければ「思ったよりお金がかかった」「こんなはずじゃなかった」と感じてしまうこともあります。
ここでは、以下の「主なデメリット」とその対策を整理してご紹介します。
- 材料費+工賃が高く、初期費用が高額になりやすい
- プラスチック系断熱材は、火災時に燃え広がるリスクがある
- 外壁が厚くなるため、間取りが制限される場合がある
順番に解説していきましょう。
材料費+工賃が高く、初期費用が高額になりやすい
外断熱は、内断熱(充填断熱)に比べて材料費や工賃が高くなりやすく、建築コストがどうしても高額になる傾向があります。
▼高性能な断熱材は材料費が高い
外断熱では、高い断熱性能と自立できる堅さを確保するために、高性能なボード状の断熱材を用います。
高性能なボード状の断熱材は、内断熱で主流のグラスウールなどに比べて材料自体の価格が高い傾向にあります。
また、気密テープや発泡ウレタンスプレーといった副資材も必要になり、内断熱よりも建築コストがかさみやすくなります。
▼施工に高度な技術と手間がかかる
外断熱は、建物を外側からすっぽりと覆う工法です。窓や扉の開口部周り、断熱材の継ぎ目、屋根との取り合いなど、細部まで丁寧に気密性確保の処理をおこなう必要があります。
そのため、施工の難易度が高く、熟練した職人の技術が不可欠です。対応できる業者が限られることもあり、結果として工賃(人件費)が高くなる傾向があります。
このように、外断熱の初期費用が高額になるのは事実ですが、以下の工夫で対策することも可能です。
- ランニングコストも入れて比較検討する
- 複数社から見積もりを取り、比較する
- 補助金を活用する
外断熱は、冷暖房効率が向上するため、毎月の光熱費を削減できます。快適に過ごせるため、医療費の低減も期待できます。
外断熱の施工実績が豊富で、価格と技術力のバランスが取れた「信頼できる建築会社」を慎重に選ぶことで、費用対効果の高い家づくりも目指せます。
国や自治体が、高い省エネ性能を持つ住宅の新築に補助金制度を設けている場合もありますので、うまく活用するとコストを相殺できます。
プラスチック系断熱材は、火災時に燃え広がるリスクがある
外断熱で用いられるボード状の断熱材は、人工樹脂(プラスチック)を発泡成形してつくられます。
人工樹脂は石油由来の有機物であるため、万が一火災が発生した場合には燃え広がるリスクがあります。
▼プラスチック系断熱材の注意点
たとえば、プラスチック系断熱材は火災時に以下のリスクが懸念されます (とくにポリスチレンや硬質ウレタン)。
- 可燃性(燃えやすさ)
- 自己消火性の限界
プラスチック系断熱材は、木材と同じく有機物を主原料としています。そのため直接火にさらされると着火・燃焼しやすい性質があります。
この点は、無機物を主原料とする断熱材(グラスウールやロックウールなど)と大きく異なります。
》硬質ウレタンフォーム断熱材とは?特徴とメリット・デメリットを解説
》ポリスチレンフォーム断熱材とは?メリット・デメリットを解説
》フェノールフォーム断熱材とは?特徴とメリット・デメリットを解説
また、多くのプラスチック系断熱材は、難燃処理が施され、火元が離れれば自然に消える「自己消火性」を持っています。
しかし、これはあくまで小規模な火災を想定したものです。火力が強い火災や長時間炎に触れるケースでは、燃焼が広がる可能性があります。
▼安心のための法規制と施工対策
日本では、この火災リスクを抑えるために、建築基準法で厳しい規定が設けられています。
延焼の危険性が高い地域では、外壁材や屋根材に不燃性の素材を使用し、断熱材が直接火に触れないように設計されるのが一般的です。
参考:建築基準法 第23条
参考:建築基準法 第61条
また、防火区画の設置やファイヤーストップ材の活用といった施工技術による工夫もおこなわれています。
つまり、きちんとした基準に基づいて施工されていれば、外断熱だからといって極端に火災に弱くなるわけではありません。
大切なのは、こうした対策を確実に実施できる、実績と技術力のある建築会社を選ぶことです。
外壁が厚くなるため、間取りが制限される場合がある
外断熱を採用すると壁の厚みが増すため、とくに狭小敷地での家づくりでは、間取りに制約が生じる場合があります。
外断熱では、建物の構造材の外側に50~100mmほどの断熱材を施工し、その上に外壁材を重ねます。その結果、壁の総厚が内断熱よりも厚くなります。
都市部のように敷地いっぱいに建物を建てるケースでは、この壁の厚みが想定以上に影響することがあります。例をあげると ⸺
- 外形寸法が大きくなり、敷地境界に接近して、施工が難しくなる
- 隣家との距離が近くなり、将来的にトラブルになるリスクがある
- 外壁や屋根の面積が増え、建築コストがアップする
このような影響を抑えるために、外断熱では、間取りに制約が生じる場合があります。たとえば、「間取りを小さくする」や「3階建てにする」などです。
ですから、外断熱を選ぶ際は、設計の初期段階から「壁の厚み」を見込んでプランニングすることが大切です。
魅力・長所も多い!外断熱ならではのメリット3選

ここまでデメリットを見てきましたが、もちろん、外断熱にはよい点もたくさんあります。むしろ、外断熱を選ぶ大きな理由はこの「メリット」にあると言えるでしょう。
ここでは、外断熱ならではの「主な3つの長所」をご紹介します。快適性や省エネ性、建物の寿命に直結する部分なので、家づくりを検討するうえでぜひ知っておきたいポイントです。
- 熱橋が少なくなり、高い断熱性能を発揮できる
- 家の構造体が外気温の影響を受けにくく、長持ちする
- 建物全体を隙間なく覆うため、気密性を上げやすい
順番に解説していきましょう。
熱橋が少なくなり、高い断熱性能を発揮できる
外断熱工法は、熱橋(ヒートブリッジ)を大幅に少なくすることが可能であり、高い断熱性能を発揮できます。結果として、冷暖房効率の向上により、光熱費の削減につながります。
熱橋とは、断熱材が途切れてしまった部分や、柱や梁といった熱を伝えやすい構造材が断熱層を貫通している部分のことです。
この熱橋があると、そこから熱が出入りしやすくなり、せっかくの断熱効果が下がってしまいます。外断熱では、この弱点を最小限に抑えることができるのです。
▼外断熱と内断熱の熱橋の違い
従来の内断熱では、柱や梁の間に断熱材を詰め込むため、どうしても構造材自体が熱橋になってしまいます。
一方、外断熱は建物全体を外側から断熱材で包み込みます。柱や梁を含めてすっぽり覆うことで、熱が構造材を通じて伝わるのを大幅に抑えられるのです。
断熱材が途切れずに連続するため、壁全体の断熱効率が高まり、冷暖房効率もぐんと上がります。
▼結露防止や建物の寿命にも効果的
熱橋が減ると、断熱性能が上がるだけでなく、結露のリスクも低減できます。
結露が減ればカビや建物の劣化を防ぐ効果もあり、快適性と耐久性の両方にプラスです。外断熱のメリットを実感できる大きなポイントと言えるでしょう。
家の構造体が外気温の影響を受けにくく、長持ちする
冬場に冷たくなった熱橋部分は、室内の空気が触れることで「壁体内結露」を引き起こします。建物の劣化の大きな原因のひとつが、この壁体内結露です。
外断熱による壁体内結露の予防は、建物の長寿命化に貢献します。長く安心して住み続けられ、メンテナンスコストの削減も期待できます。
▼結露の抑制による構造材の保護
内断熱では、室内の暖かく湿った空気が熱橋周辺で結露しやすく、カビの発生や木材の腐朽、シロアリの食害につながる場合があります。
一方で外断熱は、建物の構造体全体を断熱材ですっぽり覆うため、構造体の温度が室温に近い状態で保たれます。その結果、壁内の結露発生リスクを軽減できるのです。
▼温度変化による劣化の防止
構造体を断熱材で覆う外断熱では、外気温が直接構造体に伝わらないため、急激な温度変化や乾燥・湿潤の繰り返しによる劣化を抑えられます。
たとえば鉄筋コンクリート造では、外断熱によりコンクリートの膨張・収縮が抑制され、ひび割れ(クラック)の発生を少なくする効果が期待できます。
耐久性が高まれば、大規模な修繕やリフォームの頻度も減らせ、長期的にコストを抑える効果も見込めます。
建物全体を隙間なく覆うため、気密性を上げやすい
外断熱は、建物全体を断熱材で包み込む工法であるため、気密性を高めやすい特徴があります。
気密性が高まると断熱効果が安定し、「快適性、省エネ性、耐久性」にもよい影響を与えます。結果として、暮らしやすく、光熱費やメンテナンス費用を削減できる家になるでしょう。
気密性とは、建物の隙間をなくし、外気の侵入や室内の空気の漏れを防ぐ性能のこと。では、なぜ外断熱が気密性を確保しやすいのでしょうか?
▼断熱層が連続する
外断熱では、柱や梁の外側にシート状やボード状の断熱材を連続して施工するため、断熱材そのものが気密層として働きます。
継ぎ目も気密テープでふさぐため、内断熱に比べて隙間が生じにくいのが特徴です。
▼断熱の障害物が排除される
内断熱の場合、壁の内部には柱や筋かい、配線や配管、コンセントボックスなどが多く存在します。そのため、断熱材を隙間なく施工するのが難しくなります。
一方、外断熱はこれらの障害物の外側で気密ラインを確保します。その結果、施工ミスを減らしやすく、安定した気密性能を実現できます。
高い気密性は、断熱性能を最大限に引き出すだけでなく、結露の抑制や空気の質の改善にもつながります。
外断熱を検討する際は、「どの程度の気密性能を確保できるか」を施工会社に確認し、気密測定の実績がある会社を選ぶと安心です。
外断熱(外張り断熱)とは?内断熱(充填断熱)との違いを解説

外断熱と内断熱は、どちらも住宅の快適性や省エネ性に大きく関わる重要な工法です。どちらかが「正解」というわけではなく、最適解は人や状況によって変わってきます。
ここでは、両者の特徴を比較しながら、それぞれに向いているケースを整理してみましょう。
外断熱と内断熱の違いを表で比較
外断熱と内断熱の違いは、なんでしょうか?
外断熱は「性能重視型」、内断熱は「コスパ重視型」と考えるとわかりやすいでしょう。違いを表でまとめてみます。
| 評価項目 | 外断熱 | 内断熱 | 補足説明 |
|---|---|---|---|
| 断熱性能 | ◎ (高い) | ○ (標準的) | 外断熱で使う断熱材は、高性能なものが多い。ただし一定の厚みが必要。 |
| 熱橋 | ◎ (少ない) | △ (柱・梁) | 外断熱は構造材全体を包むため、熱橋や壁体内結露を減らしやすい。 |
| 気密性 | ◎ (確保が容易) | △ (施工に依存) | 外断熱は構造体の外側で連続した層をつくりやすく、隙間が生じにくい。 |
| 結露リスク | ◎ (低い) | △ (施工に依存) | 外断熱は壁内の温度差が小さくなるため、結露を防ぎやすい。 |
| 耐久性 | ◎ (向上) | ○ (標準的) | 外断熱は構造体が外気温から守られ、温度変化や結露による劣化を抑制。 |
| コスト | × (高い) | ◎ (比較的安い) | 外断熱は断熱材や施工のコストが高くなる傾向がある。 |
| 工期 | △ (多少長め) | ○ (比較的短い) | 外断熱は断熱・気密工事の施工に手間がかかるため、工期が長くなりがち。 |
| 間取り制限 | △ (制限あり) | ◎ (少ない) | 外断熱は外壁が厚くなるため、狭小敷地では間取りに制約が出やすい。 |
また、リフォームの容易さという観点でも違いがあります。 外断熱は室内のリフォーム時に断熱層を気にせず作業できます。一方、内断熱は外壁材の張替えや断熱材の交換が比較的しやすいのが特徴です。
外断熱と内断熱には、それぞれ一長一短があります。どちらか一方が絶対的に優れているわけではありません。大切なのは、自分に合った工法を見極めることです。
性能や快適性を優先したいなら外断熱、コストや間取りの自由度を重視したいなら内断熱というふうに、ライフスタイルや予算、敷地条件を踏まえて選ぶのが後悔しないポイントです。
外断熱はこんな人におすすめ
外断熱は、どんな人に向いているのでしょうか?
これまでの解説を総合すると、外断熱は「快適性と健康」「建物の寿命」「長期的なコストメリット」を優先したい人におすすめです。
▼快適性と健康を最優先する人
外断熱は断熱性・気密性に優れているため、家全体の温度差を小さく抑えられます。これにより冬場のヒートショックリスクが減り、体への負担も軽減できます。
参考:国立循環器病研究センター「冬場は心筋梗塞による心停止が増加」
さらに、構造体全体が温められるため壁体内結露を防ぎ、カビやダニの発生リスクを抑える効果もあります。
魔法瓶のように家全体を包み込むことで、冷暖房効率が高くなり、少ないエネルギーで快適な室温を保ちやすいのも魅力です。
▼建物を長持ちさせ、資産価値を維持したい人
外断熱は、構造体を外気温や湿気の影響から守るため、建物の耐久性を高めます。急激な温度変化や湿気による劣化を防げるため、長く住める家を求める方に人気です。
構造体の劣化が遅れれば、大規模修繕の頻度も減り、長期的に見てメンテナンスコストを削減しやすくなるでしょう。
▼初期費用よりもランニングコストを重視する人
外断熱は初期費用こそ高めですが、冷暖房効率が上がることで光熱費を大きく削減できます。長期的に見ると、生涯コスト(建築費+光熱費)でメリットが出やすい工法です。
ですから外断熱は「初期投資はかかっても、後々のランニングコストを抑えたい」と考える人に適しています。
一方で、初期費用をなるべく抑えたい人や狭小敷地での建築を考えている人にはデメリットもあるため、条件に応じて慎重に判断することが大切です。
内断熱はこんな人におすすめ
内断熱は「コストや工期を優先したい人」「都市部の狭小地に家を建てたい人」「標準的な省エネ性能でよいと考える人」におすすめです。
▼コストと工期を抑えたい人
内断熱は、外断熱に比べて材料費や施工費が安く済むため、初期費用を抑えたい方に適しています。
多くの工務店や職人が慣れている工法であるため、工期が比較的短期間で済みやすいのも大きなメリットです。
▼狭小地で建築する人
壁が厚くならない内断熱は、建物の外形寸法に影響を与えにくく、狭小敷地に有利です。
外断熱より「外壁の施工がしやすい、室内空間を確保しやすい」などのメリットがあるため、住宅が密集する都市部での建築に向いています。
▼標準的な省エネ性能でよいと考える人
現行の省エネ基準を満たすレベルの断熱性能でよいと考える場合、内断熱は合理的な選択肢です。コストと性能のバランスを取りたい方には適した工法と言えるでしょう。
内断熱によく使われるグラスウールはコストパフォーマンスに優れており、厚みを増やすことで断熱性能を高められます。
ただし、内断熱には「熱橋」や「壁体内結露」のリスクもあります。そのため、防湿層(気密シート)の施工を丁寧におこなうことが建物を長持ちさせるポイントになります。
まとめ:外断熱で後悔しないためには建築会社選びが大切
外断熱は、初期費用の高さや施工の難しさなどデメリットもありますが、断熱性能や快適性、建物の寿命といった大きなメリットも持つ工法です。
つまり「後悔するかどうか」は、工法そのものよりも、自分に合った断熱方法と信頼できる施工会社を選べるかどうかにかかっています。
外断熱は施工の精度が性能に直結するため、経験の少ない業者に任せてしまうと本来の力を発揮できません。逆に、実績豊富な会社に依頼すれば、快適で長持ちする住まいを実現できます。
失敗を避けるためには、まず外断熱に強い会社を探し、複数社に間取りや見積もりを依頼して比較することが大切です。外断熱の魅力を最大限に引き出すために、信頼できる会社を選びましょう。