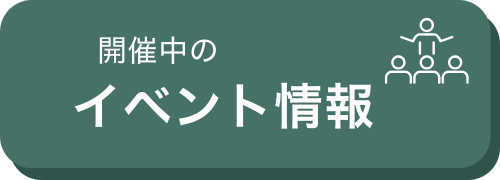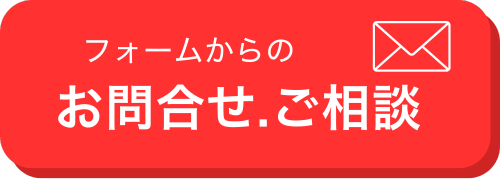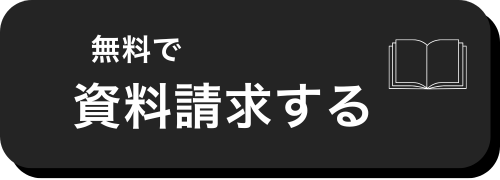新築するなら、快適な家にしたいですよね。そんなときに参考になるのが《断熱等級》で、現在の新築住宅は等級4以上にする必要があり、2030年には等級5以上が義務付けられる予定です。
では、等級5なら快適に過ごせるのでしょうか?⸺ 結論から言うと、そうとも限りません。さまざまな要因により、等級5でも冬は「寒い」、夏は「暑い」と感じる場合があります。
本稿では、断熱等級5の家でも「寒い・暑い」と感じる理由や、等級6・7との違いについてわかりやすく解説します。「快適な家にしたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
断熱等級とは、住宅の断熱性能を示す指標
断熱等級をご存じでしょうか?そもそも「断熱」とは何でしょうか?
まずは、断熱と断熱等級についておさらいしておきましょう。断熱の仕組みを理解しておくと、あなたの家づくりにきっと役立ちます。
そもそも断熱とは

住宅における「断熱」とは、外気と室内のあいだの熱の移動を少なくすることを指します。断熱性を高めると、住宅の快適性や省エネ性が向上します。
熱は高いほうから低いほうへ移る
熱には、高いほうから低いほうへ移る性質があります。そのため、住宅では以下のことが起こっていて、冬には「寒い」と感じ、夏には「暑い」と感じます。
- 冬:室内の熱が屋外に流出する
- 夏:屋外の熱が室内に流入する
この熱の移動をできるだけなくそうとするのが「断熱」です。具体的には、家の外皮に熱伝導率が低い(熱を伝えにくい)建材を使用して、熱の移動を妨げます。
「外皮」とは、建物の外部と内部を隔てる境界のことです。住宅の場合は、外壁・屋根・床・窓などが外皮にあたります。
なお、熱の流出入の半分以上は窓で生じています。ですから、窓の断熱性を高めることが、住宅全体の断熱性能に大きく影響します。
参考:日本建材・住宅設備産業協会「開口部からの熱の出入りは、どの位あるのですか?」
断熱のメリット
高断熱住宅は「魔法瓶のような家」、あるいは「クーラーボックスのような家」と言われます。
そのような家の主なメリットは以下のとおりです。
- 光熱費を削減できる
- 健康効果が期待できる
- 補助金や税制の優遇がある
高断熱住宅は室内温度を一定に保ちやすく、冷暖房効率が向上します。そのため、少ないエネルギーで《夏は涼しく、冬は暖かい環境》を維持できるため、光熱費を削減できます。
また「脱衣所だけヒヤッとする」「寝室が寒くて起きづらい」といった屋内の温度差も少なくなります。ヒートショックのリスク軽減や、結露防止によるカビやダニの発生抑制にも役立ちます。
さらに、一定の省エネ基準を満たす新築や建て替えには、補助金や税制優遇、低金利ローンなどさまざまな支援策が用意されています。
なお、断熱性能を最大限発揮するには、気密性と計画的な換気も重要です。
気密性が低いと隙間から熱が流出入し、断熱効果が損なわれます。一方、気密性が高い住宅においては、換気が不足するとシックハウス症候群などの健康被害に遭うリスクがあります。
断熱性を表わす主な指標
現在、断熱性を表わす際、主に《UA値》と《ηAC値 (イータエーシーち)》が使われています。
| UA値 | 外皮平均熱貫流率。建物全体の外皮を通じて逃げる熱量を表わす。値が小さいほど断熱性能が高いことを意味する。 |
|---|---|
| ηAC値 | 冷房期の日射取得率。主に夏場の冷房負荷を評価するために用いられる。値が低いほど日射熱が入りにくく、冷房効率がよい。 |
本稿のテーマである「断熱等級」も、この2つの指標によってランク付けされています。詳しく解説しましょう。
断熱等級の概要

断熱等級(断熱等性能等級)は、住宅の断熱性能を示す指標です。国土交通省が定めています。
断熱等級は1~7まであり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを示します。等級ごとにクリアすべきUA値やηAC値などの基準値が設定されており、基準値は地域ごとに差があります。
詳しい基準値は、以下のサイトで確認できます。
日本では2000年に「住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)」が施行され、断熱等級制度が開始されましたが、当初は等級1~4の4段階でした。
その後、2022年4月に等級5、10月に等級6と7が新設されました。2025年4月からは、すべての新築において等級4以上の適合が義務化されています。
さらに、2030年には等級5以上の適合が義務化される予定です。これから家を建てるなら等級5、できれば等級6を目指すのがおすすめです。
断熱等級5とは、ZEH基準相当の断熱性能
断熱等級5とは、一体どの程度の性能なのでしょうか?その特徴を、メリットとデメリットの観点から解説したいと思います。
等級5のメリット

断熱等級5は、ZEH(ゼッチ)の断熱基準に相当します。
ZEHは「Net Zero Energy House」の略で、年間のエネルギー消費量を正味ゼロ以下、つまり《太陽光発電等でつくるエネルギー》が《消費するエネルギー》を上回る住宅を指します。
従来の住宅に比べ、断熱等級5の家には以下のメリットがあります。
- 暖熱等級4以下の住宅と比べると光熱費が下がる
- 断熱等級6や7に比べて、低いコストで実現できる
- 省エネで家計負担が減り、エネルギー危機への耐性が付く
- 室内の快適性の向上により、病気になるリスクが下がる
- 病気になるリスクが下がることで医療費の低減が期待できる
このように経済面・環境面・健康面でメリットが大きいところが、断熱等級5の魅力です。
また、2030年にはすべての新築住宅に等級5の適合が義務化される予定です。つまり、断熱等級5の家を建てておくと、2030年の義務化の際にも基準を満たし続けられます。
一方、断熱等級4以下の家は既存不適格となる可能性が高いです。既存不適格とは、建築当時は適法だったものの、法改正などにより現行法規に適合しなくなった状態のことを指します。
既存不適格住宅は違法ではないため、所有してもペナルティはありません。しかし、大規模リフォームの際に適法化を求められたり、売れにくくなったりする可能性があります。
等級5のデメリットと注意点
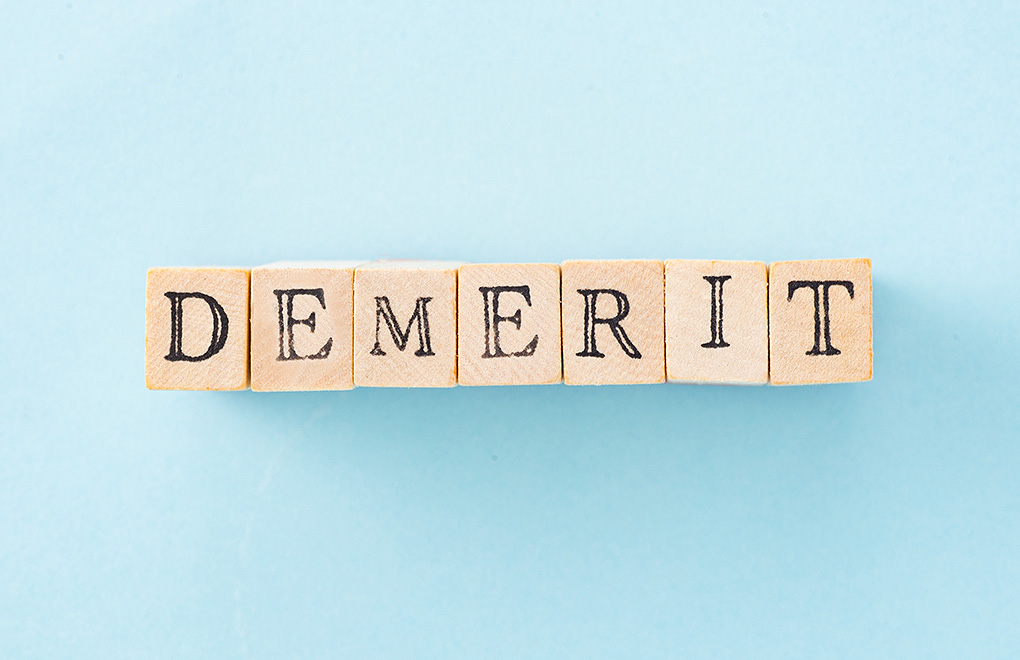
断熱等級5の住宅には、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。
代表的なものをご紹介しましょう。
- 建築費用が高くなる
- 断熱性が不足する場合がある
- 窓の大きさや数に制約が出る可能性がある
- 気密と換気に気を配る必要がある
- より施工業者選びが大切になる
それぞれ、もう少し詳しく解説します。
建築費用が高くなる
断熱等級の高い家は、建築費用が高くなります。なぜなら、断熱等級を高めるためには、断熱性能の高い効果な建材を使用する必要があるからです。
たとえば、断熱グレードの高い窓を使用したり、壁や天井に熱伝導率の低い断熱材を入れたりする必要があります。施工の難易度も上がるため、手間賃も増えます。
断熱性が不足する場合がある
断熱等級5にすると、従来の家より断熱性能がグレードアップします。とは言え、断熱等級6や7の家と比べると、まだ断熱性を上げる余地があるレベルです。
ですから、寒さ・暑さに敏感な方にとっては、じゅうぶんな性能ではない可能性があります。真冬は「寒い」、真夏は「暑い」と感じる場合があるでしょう。
窓の大きさや数に制約が出る可能性がある
窓は家の中で熱の出入りが最も大きい部分です。そのため、断熱性能を上げるには、窓の数や大きさに制約が出る場合があります。
大開口の窓をたくさん設けたデザインの家にするときは、ガラスやサッシ枠の断熱グレードを高くする必要があります。その結果、コストも上がるでしょう。
気密と換気に気を配る必要がある
断熱性能を高めた住宅では、同時に気密性もしっかり確保する必要があります。せっかく高性能の断熱材を入れても、家に隙間が多ければ熱が流出入してしまい、その性能を生かせません。
また、気密性が高まる分、計画換気(機械換気や通風設計)で湿気や汚れた空気を排出する工夫も必要です。
より施工業者選びが大切になる
高気密・高断熱住宅は高度な施工技術を要するため、経験が浅く実績の少ない建築会社だと性能を出し切れない恐れがあります。
たとえば、断熱材の充填の甘さや気密処理のミスなど、小さな施工不良が積み重なると性能が落ちてしまいます。ですから、従来の住宅以上に建築会社選びが重要です。
断熱等級5の家が寒い理由とは?
インターネットの口コミなどを見ていると「断熱等級5の家でも寒い」といった書き込みを見かけることがあります。
これは一体どういうことなのでしょうか?
立地や気密性によっては寒さを感じる

じつは、断熱等級5であっても、条件によっては寒さを感じることがあります。影響を及ぼす可能性のある条件をご紹介しましょう。
立地条件
日本は、地域によって気候が大きく異なります。そのため、断熱等級5の基準値自体、北海道のような寒冷地では厳しく、沖縄のような温暖地ではやや緩く設定されています。
とは言え、同じ基準が適用されている地域でも、場所によって想定される最低気温が違います。寒冷地では、等級5の性能でもなお寒さが残る可能性があります。
気密性
どんなに高性能の断熱材を使用しても、家に隙間が多いと暖かさは逃げてしまいます。等級5相当の断熱仕様でも、気密性が低い家だと「なんだか寒いな」と感じるでしょう。
逆に言えば、きちんと気密測定をおこないC値が低い(隙間が少ない)と確認された家であれば、等級5の性能が生きて快適さが増します。
間取り
家の設計によっても、寒さの感じ方は変わります。たとえば、玄関ホールとリビングが仕切りなく直結している間取りでは、ドアを開けたとき外気がリビングに直接入り込み寒いでしょう。
大きな吹き抜け空間がある家も、暖気が上に逃げて足元が冷える原因になることがあります。南向きの窓が少なく日当たりが悪い家も、日中に太陽熱を取り込めず、室温が上がりにくいです。
暖房器具
断熱等級の高い家でも、まったく暖房なしで真冬を過ごせるわけではありません。「高断熱だから」と油断して暖房を控えすぎると、さすがに寒く感じます。
広い部屋なのに小さな暖房器具しか使っていない場合も、部屋全体が暖まりません。断熱性能に応じた適切な暖房器具を、適切な量だけ使う必要があります。
個人の感じ方
人によって、適温と感じる温度が違います。たとえば、寒がりの人は20℃でも寒いと感じますし、暑がりの人は18℃でも暑いと感じるかもしれません。
過去の体験も影響します。ずっとマンションで暮らしていた人は、一戸建てに引っ越すと「寒い」と感じるかもしれません。マンションは周りを隣戸で囲まれているため、断熱では有利です。
以上のように、断熱等級5の家でも状況しだいで寒く感じることがあります。しかし、それは見方を変えれば「工夫しだいで寒さを和らげられる可能性がある」とも言えます。
対策は、いろいろ考えられます。例をあげてみましょう。
- 思い切って等級6にしてみる
- 間取りを工夫して寒さを和らげる
- 断熱・気密施工に強い業者に依頼する
- 寒さが厳しい日は補助的にヒーターを併用する
「等級5にすれば大丈夫」と油断するのではなく、住まいを暖かく保つ工夫をトータルで考えることが大切です。
断熱等級6・7との比較

断熱等級6や7は、現在の日本では最高レベルの断熱性能基準です。等級5と、どのくらい違いがあるのでしょうか?
断熱等級5と断熱等級6・7の違いは、客観的に見ると「UA値」の基準値の差にあります。一例として、地域区分6(東京等)の地域で比較してみましょう。
| 断熱等級 | UA値 | ηAC値 |
|---|---|---|
| 等級5 | 0.60以下 | 2.8以下 |
| 等級6 | 0.46以下 | 2.8以下 |
| 等級7 | 0.26以下 | 2.8以下 |
では、等級5~7の家は、暮らしにどのような違いをもたらすのでしょうか?⸺ それぞれ、等級4と比較したときの冷暖房費削減率を見てみましょう。
- 等級5:約10%の冷暖房費削減が期待できる
- 等級6:約50%の冷暖房費削減が期待できる
- 等級7:約70%の冷暖房費削減が期待できる
冷暖房費は、等級6・7の家のほうが相当に削減できそうです。とは言え、等級6・7の家は建築コストが上がります。
ランニングコスト(維持費用)が下がったとしても、イニシャルコスト(初期費用)も合わせたトータルで見るとどうなのでしょうか?お得なのでしょうか?
これに関しては、等級4と比較した以下のような試算があります。
| 費目 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 施工費 | +63万円 | +119万円 | +307万円 |
| エアコン | ±0万円 | ▲90万円 | ▲90万円 | |
| 維持費用 (30年) |
光熱費 | ▲43万円 | ▲62万円 | ▲89万円 |
| 医療費 | ▲86万円 | ▲134万円 | ▲200万円 | |
| 削減効果額 | ▲66万円 | ▲167万円 | ▲72万円 | |
いずれも、30年暮らすと等級4よりお得になると試算されています。一方、等級7は施工費の増加額が大きく、削減効果は等級6が一番高くなっています。
上述のような断熱性能を持つ等級5~7の家をひと言で表わすと、以下のようになります。
- 等級5:省エネ(省光熱費)で快適に暮らせる住宅を実現可能
- 等級6:省エネで快適、かつ費用対効果も非常によい
- 等級7:極めて快適かつ高い省エネ性だが、施工コストも高い
長期的な費用対効果では、等級6や7にするメリットがあると言えます。とりわけ等級6は、施工費の増加分を相殺して余りあるメリットが期待できます。
2030年以降の新築住宅では、断熱等級5が当たり前、等級6・7が高断熱住宅になる予定です。等級5に不安を感じる方は、積極的に6や7レベルを目指してみてはいかがでしょうか。
まとめ:断熱等級5の家が寒い理由
断熱等級5の住宅は、高い快適性と省エネ性を実現できます。一方、立地や気密性、間取りなどの条件によっては「寒い」と感じる可能性があります。
本稿をご覧いただき「等級5では少し不安だな」と感じた方は、さらにハイグレードの等級6や7を目指してみてはいかがでしょうか。より快適に、より少ない光熱費で生活できるようになるはずです。
また、高気密・高断熱住宅を建てる際は、実績豊富な建築会社を選ぶことも大切です。気密性(C値)を測定してくれて、断熱に関するさまざまなアドバイスをくれる会社が望ましいでしょう。
三原防水ドット工務では、断熱等級5以上の住宅のご相談を承っております。「断熱等級のことを詳しく知りたい」「新築のプラン図面が欲しい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。